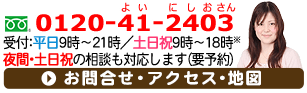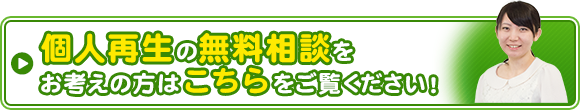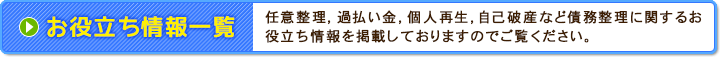「個人再生」に関するQ&A
配偶者の個人再生手続による影響にはどんなものがありますか?
1 配偶者は影響を受ける可能性があります
個人再生は、支払うべき借金を大幅に減額することのできる債務整理手続です。
家族と暮らす住宅ローン支払い中のマイホームを、ローン債権者に処分されないように手続きをすることもできるという大変便利な制度となっています。
しかし、裁判所を用いた厳格な手続きが必要なうえ、減額された借金の返済を確実に履行する必要があります。
そのため、配偶者が個人再生手続をした場合、その影響を受けてしまうおそれがあります。
ここでは、その場合に考えられる家族への影響と対応策を説明します。
2 個人再生はどのような手続きか
個人再生は、借金を支払えないおそれがある債務者が、借金の一部について、原則3年(最長5年)にわたり分割して返済する再生計画案を裁判所に認可してもらうことが目的です。
その後、債務者が再生計画に従った返済を完了すれば、残る借金は免除されることとなります。
もし、再生計画により圧縮された借金の返済にすら失敗してしまった場合には、個人再生が取り消され、残る借金が復活してしまうおそれがあることに注意が必要です。
個人再生手続では、自己破産と異なり、裁判所が債務者の財産を処分する必要はありません。
ただし、ローン支払い中の車など、担保権がついている財産は、債権者により処分(引き揚げ)されてしまいます。
なお、個人再生手続では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度により、マイホームを処分されないように手続きをすることができます。
もっとも、住宅資金特別条項を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
【ペアローンの場合は特に注意】
住宅資金特別条項を利用するには、債務者が住宅を所有しかつ居住していることなどが必要となりますが、特に、ペアローンのように夫婦で住宅ローンの負担を共にしている場合には、注意が必要です。
夫婦のいずれかのみが住宅ローンを単独で負担し、もう片方が住宅ローンについて連帯保証人になっている場合や、連帯債務(一つの借金を複数人で一緒に負担するもの)にしている場合は、住宅資金特別条項を利用することができます。
しかし、ペアローンの場合、住宅ローンや抵当権は、それぞれ合計二つあることになります。
そのため、マイホームに「債務者が負担している住宅ローン以外の借金についての抵当権」が存在することになり、住宅資金特別条項の利用条件に反してしまいます。
もっとも、実務上は、夫婦共同で個人再生手続の申立てをすれば、住宅資金特別条項を利用することは認められています。
詳しくは弁護士にご相談ください。
3 配偶者の個人再生による影響
⑴ 返済への援助が必要な可能性
個人再生では、裁判所に認めてもらった再生計画に従い、原則3年(最長5年)のうちに返済を完了しなければなりません。
失敗すれば借金は復活し、ほとんどの場合、自己破産するしかなくなります。
そうなると、住宅資金特別条項により維持していたマイホームも処分されてしまいます。
再生計画の履行可能性の判断や、現実の履行においては、配偶者の収入を考慮することが可能です。
よって、夫婦共同生活の場であるマイホームを維持するためにも、配偶者の個人再生計画履行について、金銭的な援助をする必要が出てくる場合があります。
なお、このような理由から、個人再生では配偶者の収入を証明する資料も裁判所に提出する必要があります。
⑵ 自動車を手放す必要がある可能性
先ほども軽く触れましたが、自動車ローンが残っている自動車は、個人再生手続をすると債権者に処分(引き揚げ)されてしまいます。
自動車がなくなると困るということで、自動車ローンだけでも先に返済してしまおうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、特定の債権者への優先弁済は、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、債権者平等の原則に反するものとして禁止されています。
(※公的機関である裁判所を用いる個人再生手続では、債権者は平等に取り扱わなければなりません。これを「債権者平等の原則」といいます。)
自動車を維持するには、債務者ではない人が自動車ローン残高を支払うという方法があります。
配偶者であれば、債務者本人ではありませんので、この方法をとることは可能のように思われます。
ただ、配偶者が支払うにしても、同一家計、同一世帯からの出費は避けた方がよいです。
債務者から配偶者へお金を渡し、配偶者名義で返済しても、実質的には債務者本人が支払ったようなものですから、偏頗弁済の疑いが生じてしまうからです。
そのため、配偶者以外の方に支払ってもらうのが理想ではありますが、配偶者以外にあてがなく、配偶者から支払うということであれば、あくまで、配偶者本人の個人的な財産から支払いきる必要があります。
⑶ 連帯保証人になっていると一括請求される可能性
個人再生をすると、減額された借金の債権者は、その借金の保証人(連帯保証人)に、債務の全額の一括返済を求めます。
個人再生の効果は債務者本人にのみ及ぶので、保証人(連帯保証人)への請求分までもが減額されることはありません。
そのため、配偶者が保証人となっている債務があれば、個人再生をすることで、配偶者は一括での返済を求められます。
とはいえ、一括請求が現実的に厳しい場合は、分割払いの交渉をすることになると考えられます。
分割が認められれば、保証人も債権者に分割で債務を返済していくことになります。
たとえば、もともとの債務が500万円あり、主債務者である夫が個人再生をして5分の1の100万円が再生債務になったとします。
この場合、夫は100万円を、保証人である妻は500万円を並行して分割返済していくことになるのですが、両者の返済額の合計が500万円になった時点で、主債務者も保証人もそれ以上の支払義務はなくなることになります。
個人再生は先述のとおり、債権者平等の原則があるので、配偶者を保証人としている債務のみ手続きから外すというようなことはできません。
この点、任意整理なら、保証人のいる債務を手続きから外すことは可能です。
4 個人再生手続と離婚
個人再生手続をするほどの借金をした相手とは離婚したい、あるいはすでに離婚したという場合もあるかと思います。
最後になりますが、個人再生手続が離婚にどのような影響を及ぼすのかを解説します。
【配偶者の個人再生手続を理由とした離婚は可能?】
そもそも「配偶者の借金が理由で離婚ができるのか?」と疑問の方もいらっしゃるかと思います。
協議による離婚であれば、理由に制約はありません。
妻や夫の借金や個人再生を理由として離婚できます。
しかし、協議による決定ができず、裁判所に離婚を認めてもらおうとした場合、個人再生手続をしたことそのものは離婚事由として認められません。
借金をした原因が浪費やギャンブルであったなど、婚姻生活を継続することが難しいといえる事情が必要です。
個人再生をしたという事実だけでは、法的に履行を認めてもらうことはできないのです。
⑴ 養育費
個人再生手続開始決定前に生じていた未払いの養育費(延滞している養育費)については、個人再生の再生計画に基づく分割払いを終えた後に、残額を一括して支払ってもらうことができます。
養育費は、個人再生などの債務整理をしても支払いが免除されることはありません。
もちろん、手続開始決定後の将来支払う養育費についても、当然ながら手続き中・手続き後に請求できます。
⑵ 慰謝料
離婚の慰謝料を受け取れるかという点が気になる方もいらっしゃると思いますが、借金・個人再生が原因の離婚の場合、満額の慰謝料を受け取ることはできないと考えられます。
他にも、性格の不一致や、浮気が原因の慰謝料は、普通の借金同様、個人再生手続の対象となり、個人再生により減額されます。
一方で、暴力をふるって元配偶者を傷害していた(DVをしていた)場合、再生計画による分割払いを終えた後に、残額を一括請求できることになります。
なお、暴言によるDVでも、同様の扱いがされる可能性があります。
5 配偶者が個人再生をお考えならご一緒に当法人へ
個人再生は、夫婦の共同生活の場となるマイホームを維持し、また、担保権の付いていない重要な財産も処分されずに済む大変便利な債務整理手続です。
しかし、住宅ローンを夫婦でどのように負担しているかによっては、複雑な問題が生じてしまうおそれがある手続きでもあります。
個人再生に限らず、借金問題の解決のためには、できる限り早く、債務整理に精通した弁護士に相談し、その助言を受けることが大切です。
どうぞ、ご夫婦で弁護士へとご相談ください。
当法人では、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。
借金問題の相談は原則として無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
個人再生手続きが終わった後,約束どおりの支払いができなくなったら,どうなるのですか? できるだけ自己破産はしたくないのですが?